多様な学びの選択肢が親子を救う!?
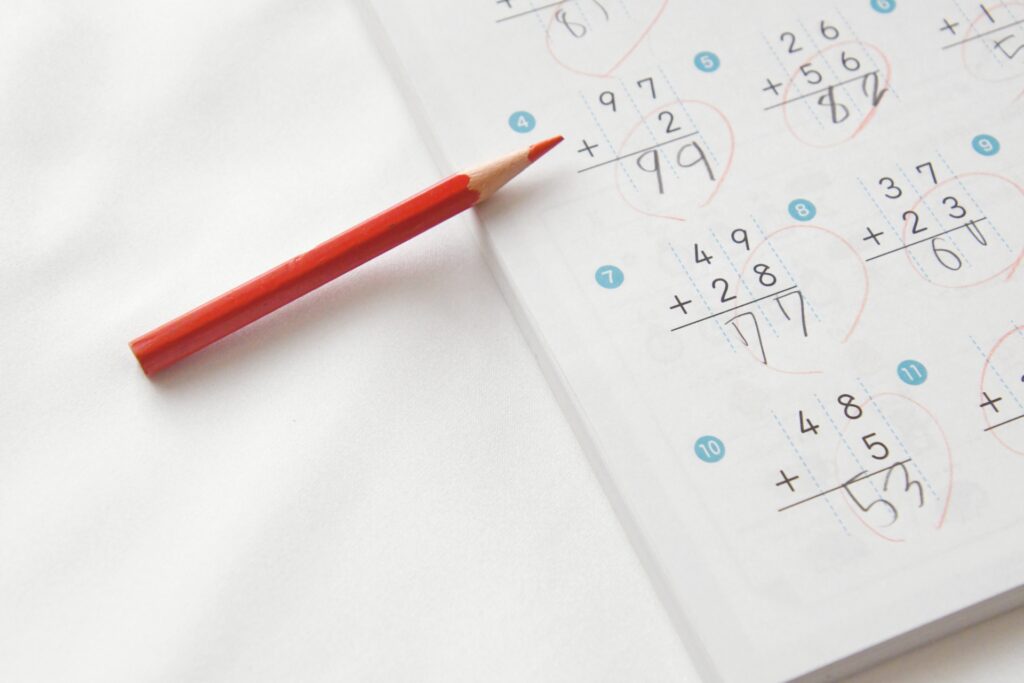
赤ちゃんの頃から「じぃじLOVE」だった息子。不安なことがあると「じぃじに会いたいよ~」と泣き叫び、2歳半くらいになると「じぃじと結婚する」と言っていたほどだ。
ママ(私)への執着がなく、卒乳のときでさえも驚くほどあっさりしていた。1歳2ヶ月を迎えた頃、自分の中で「これで最後」と決めていた授乳を終え、息子にその旨を伝えると笑顔で私の胸にバイバイと手を振った。それでも彼が本当に理解できているのか半信半疑だった私は、翌日からしばらくの間、就寝時間の1時間ほど前から別部屋に身を潜め様子を伺っていた。もし、泣き出すようなことがあったら、卒乳は先送りにしようかとも考えていた。が、息子はパパと楽しそうにハシャギながら、そのまますんなり就寝。「ママは?」と私を探す様子さえ見せなかったようだ。
そんな息子が最近になって、「ママちゃ~ん」と甘えた声を出すようになった。一緒に寝るのも、歯ブラシも「絶対ママじゃなきゃダメ!」と言い始めた。空前のママブーム到来だ。そして、ついには「ママと結婚する!」と。彼の未来の花嫁の座をようやく“じぃじ”から奪い取ったのだ(笑)
しかし、その喜びも束の間、1つ困ったことがある。息子が「ママと一緒にいたいから」と登園を渋り始めたのだ。以前は休みの日でさえも保育園に行きたがっていた。それが最近では毎朝のように、「今日はお休みして、ママと一緒に遊ぶ」と言うのだ。「ママは、今日はお家でお仕事なんだよね?それなら僕もお家にいていいでしょ?」と、そのまっすぐな瞳にじっと見つめられると、「じゃ、今日はお休みしてママと過ごそうか!」と言ってしまいたくなる。そんな言葉が喉まで出かかっては慌てて飲み込み、「いかんいかん、ここで甘やかしてはサボり癖がついてしまうのでは?」と心の中で葛藤を繰り返す。私は親として、どう対応すべきなのだろうと。
根性論の時代は終わった!? 大事なのは子どもの気持ちにどう寄り添うか
私自身はいわゆる「根性論」で育てられてきた。昔から運動が苦手で走るのも遅く、初めてのマラソン大会では80人中72位。後ろから数えた方が早いくらいの順位であった。そんな私に両親は通学前に自主トレするよう言いつけた。マラソン大会の2ヶ月前になると、毎朝いつもより30分早く起きて、家の周りを走る。そんなことを5年間続けた。結果、小学校最後のマラソン大会では47位まで順位を上げることができた。元々、持久走が得意だった妹は、自主トレの成果もあってこの年ついに1位の栄冠を手に。47位と1位・・・同じ姉妹なのにこうも違うのかとも思うが、この経験は苦い思い出としてではなく、むしろ「努力は必ず報われる」という一種の成功体験として私の記憶に残っている。
こうした家庭環境で育ってきたからか、学生時代にも社会人になってからも、周りからは「頑張り屋」「我慢強い人」だと言われてきたし、自分自身の認識もそうであった。が、世の中の風潮として、一生懸命頑張ることだけを美徳とする考え方は古い気もする。これまでの経験上、肩の力を抜くことも大切だと思う。自分の好きなことを見つけて、努力することは大切。でも、何でもかんでも一律に頑張ればよいというわけではないか、と。いまはまだ保育園の段階なので問題はそこまで深刻ではないが、義務教育が始まった後に息子が同じように「行き渋り」を見せたら、どうすればよいのだろう・・・
悶々とした思いを抱えたまま日々を過ごしていると、日経 x womanの記事「不登校・行き渋り 親の心構えー不登校増える背景に、学校教育への不満がある」が、目に飛び込んできた。
内容はざっとこんな感じだ。
・これからの時代、企業が求めているのは何か1つ秀でた個性のある人材だが、いまの学校教育ではそういった人材がうまく育たない
・学校の勉強に魅力が乏しく、コロナ禍の影響などもあり「行き渋り」が増加
・フリースクールやICTでの学習支援などもあり、「登校への呪縛」から解放される親も増加
・子どもが学校に行きたがらないときは、子どもや自分を責めず、「行きたくない気持ち」を受け止めて、どう感じているのかを話し合うことが重要
「学校だけがすべてじゃない」そんな世の中になりつつあることを知った。将来、もし息子が「行き渋り」を見せたとしても、フリースクールやICTでの学習支援など多様な学びの選択肢を親がもっておけば、道は開けるかもしれない。私自身も、そこまで思い詰めることなく、心に少し余裕をもって子どもと向き合えるのかもしれない。そう思えた。
今朝も登園したがらない息子を「ママと一緒にいたいよね。できるだけ早く迎えに行くから、帰ってきたら、また一緒に遊ぼうね」となだめながら、車に乗せて出発。が、いざ園に着くと、友達とハシャギながら私には見向きもせずに駆け出していく息子。先ほどのやりとりはいったい何だったのか(笑)と一抹の寂しさを覚えながら、たくましささえ感じるその背中を見送る毎日である。


